令和7年2月13日、高知県産業振興センターにおいて「IoP技術者コミュニティ成果発表会」が開催され、令和6年度データ連携基盤活用実証事業委託業務の報告会が実施されました。IoP技術者コミュニティは、県内外の企業48社が参画する「IoPクラウドに関連する技術的知見が得られ、具体的な技術の習得ができる組織」をコンセプトにしたコミュニティです。参加者が業種や組織の壁を超え、楽しみながら新たなテクノロジー分野に挑戦、スキルアップに励んでいます。
今回の報告会では、IoPクラウドを利用した新たなアプリ・サービスのアイデアソンに参加したチームを中心に、成果発表やディスカッション等を行いました。高知県内の企業をはじめ県外企業も参加、また高知工科大学からは学生チームも加わり、農業分野におけるデジタル化やクラウド・AI技術の活用等の展望について、様々な取組事例の発表がありました。


IoP技術者コミュニティ成果発表会の隣の会場では、IoP技術者コミュニティ関連機器等の展示と併せて、アイデアソンの各チーム発表ポスターを展示。展示コーナーを訪れた関係者の間で、それぞれの取組について質問する様子や機器の機能について熱心に聞き入る様子が見られました。


●SAWACHI営農アプリ・サービスアイデアソン実施報告
IoPクラウドを活用したアプリやサービスの開発を目的としたSAWACHI営農アプリ・サービスアイデアソンについて、高知工科大学の学生チームを含む合計8チームが、各々の実施内容や成果・課題について発表を行いました。
1.(株)高知電子計算センター
営農コミュニティ掲示板「SAWACHI宴会場」
・背景と目的
現在、SAWACHIには利用者同士が交流できる機能が不足していることから、SAWACHI利用者が営農に関する情報を気軽に質問でき、情報を共有するこが可能な営農コミュニティ掲示板を作成。高知県内の営農コミュニティ形成・新規就農者の技術向上および、コミュニティへの加入を促進する。
・今後の展望、課題に感じたことなど
AIによる自動回答やカメラ・音声入力の活用をはじめ、共感・評価機能やアクセスランキングといった利用者の意欲を高める機能等を搭載し、SAWACHIのさらなる利用価値向上を目指していきたい。
2.(株)SHIFT PLUS
音声・動画入力による農家さんの実作業の可視化と技術継承
・背景と目的
日本の農業は、高齢化や後継者不足という深刻な問題に直面している。その原因となっている技術習得・継承の難しさや、自然相手の生産・収益化の不安定を解消するため、音声・動画入力と生成AIを活用して農家の実作業をナレッジ化し、技術継承を促進。同時にSAWACHIのデータと組み合わせて収穫量の予測を立て、収益の安定化に寄与する。
・今後の展望、課題に感じたことなど
本プロジェクトで培ったデータ活用技術やノウハウ伝承の仕組みは全国規模での展開が期待でき、日本全国での農業効率化や知識伝承、さらには他の業界での展開による新たな価値創出にも役立つと考えられます。
3.(株)カミノバ
農業事例共有サイト
・背景と目的
農業技術や市場情報はインターネット上に分散しているため、小規模農家や新規参入者は効率的に情報を取得できない現状にある。そこで、農業者や農業に関心を持つ人々がつながるためのプラットフォームを作成し、農機具や資材のレビュー機能やブログ作成機能、出荷量等を提供。プラットフォームにおける知識や経験の共有を促進し、課題解決につなげる。
・今後の展望、課題に感じたことなど
今後、農業者同士で情報共有がしやすくなることで、農業の効率化が進むと考えられる。最終的には、知識や技術の共有が進むことで、全体的な農業技術の向上が実現し、農業全体の発展につながることに期待している。
4.パシフィックソフトウエア開発(株)
SAWACHIによる収穫物の歩留まり管理
・背景と目的
作物の生産から出荷までに発生するロスに関しては、いつ、どの程度発生するのかについて、数値的な把握ができていないのが現状である。そこで今回、SAWACHIのデータを活用して、農作物ロスの数値的な把握や、ロスの発生フェーズの可視化を目指し、収穫物のロスを減少させて、効率的な農作物の生産につなげる。
・今後の展望、課題に感じたことなど
収穫漏れによる重複カウントや、収穫適期のズレによる精度に課題が生じたため、今後は個別追跡や収穫時のサイズ設定などを行うことで対応していきたい。また、多くの農家が参加することで、マクロ視点での対策なども可能になると感じている。
5. 高知工科大学【学生チーム】
SAWACHI利用者間データ共有の検討
・背景と目的
現在、SAWACHIには必要な範囲にのみ情報を公開する仕組みがなく、適切な情報共有が難しい。また人手や機材を一元管理するシステムもないため、資源の過不足も懸念される。そこで、SAWACHIにユーザごとの権限設定を設け、安全かつ容易な情報共有を実現。グループ単位のチャット機能を通じて栽培技術や収穫情報の交換を促し、新規就農者の参入やコミュニティ活性化を支援する。
・今後の展望、課題に感じたことなど
円滑な情報共有を促進するグループ機能と、リソース管理を支援する資源管理機能だが、実際の運用においては、両機能を統合することで生じる課題や、逆に独立させることで得られる柔軟性も考慮する必要があると感じた。ふたつの機能が相乗効果を発揮できるかを検証する必要があると考えている。
6.(株)アクト・ノード
SAWACHIによる公益性の高いデータの共有化と活用
・背景と目的
デジタル技術の導入やスマート化が進展している一方で、各生産者が技術を活用する際の難易度は依然として高く、設備投資にかかるコストも大きい。このため、地域で利用可能な環境データや生産者のリアルタイムデータをSAWACHIで共有することで、地域の公益性の高い取り組みへの活用を実現し、技術導入に伴う生産者のコスト削減に貢献する。
・今後の展望、課題に感じたことなど
SAWACHI経由で利用可能なデータの拡充と、簡単に使えるようにするためにもデータ利用に関する障害除去が必要と感じた。データの属性に「公開」「特定用途のみ利用可」など、データの所有者の意に反した利用リスクを取り除く仕組みを実装し、安心してデータを提供できる環境の整備を検討していく。
7. 井上石灰工業(株)【スウィーティア Fusion Grow】
AIを活用した高品質・高単価青果の収量予測システム
・背景と目的
現在、環境・栽培・品質データを基に収量予測を行いながら高品質トマトを栽培しているが、「栽培者の感覚におる予測」が最も精度が高い状況にある。そこで、栽培データとSAWACHIの環境データを活用した収量予測の簡易版アプリを開発し、これをたたき台として、栽培者目線での改善点や必要な機能などを反映した実用的なアプリケーションを設計。
・今後の展望、課題に感じたことなど
長期間における予測精度が課題となったため、特微量エンジニアリングやパラメータ設計により精度の向上を目指したい。また、各農家が保有しているデータを標準化し、SAWACHIに集まる環境データと、個別の栽培者が持つ栽培・品質データが統合されると、データ活用は今後さらに容易になっていくと感じた。
8.高知県
施設ニラにおける作付計画等個票の作成支援
・背景と目的
高知県で栽培されているニラは、1年の間に複数のハウスで作付を行い、一度定植した株から、1作のうちに5~7回の収穫を行う。複数のハウスを適切に管理し、季節に応じて適期に収穫を続けるため、計画的な作付計画と収穫作業をサポートするための個票を作成。個票作成のための出荷データ収集にSAWACHIを活用し、生産履歴と販売データを組み合わせることで省力的なデータ活用の実現を目指す。
・今後の展望、課題に感じたことなど
個票作成には手書きの生産履歴からデータを収集する必要があり、OCRリーダーによる省力化が難しいことから、必要な情報を生産者に直接SAWACHIに入力してもらうことで個票作成の負担を軽減することを目指した。現在のフォーマットはニラでの利用を想定しているが、複数の圃場で年間に何度も作付けや収穫を行う品目での応用が期待できる。


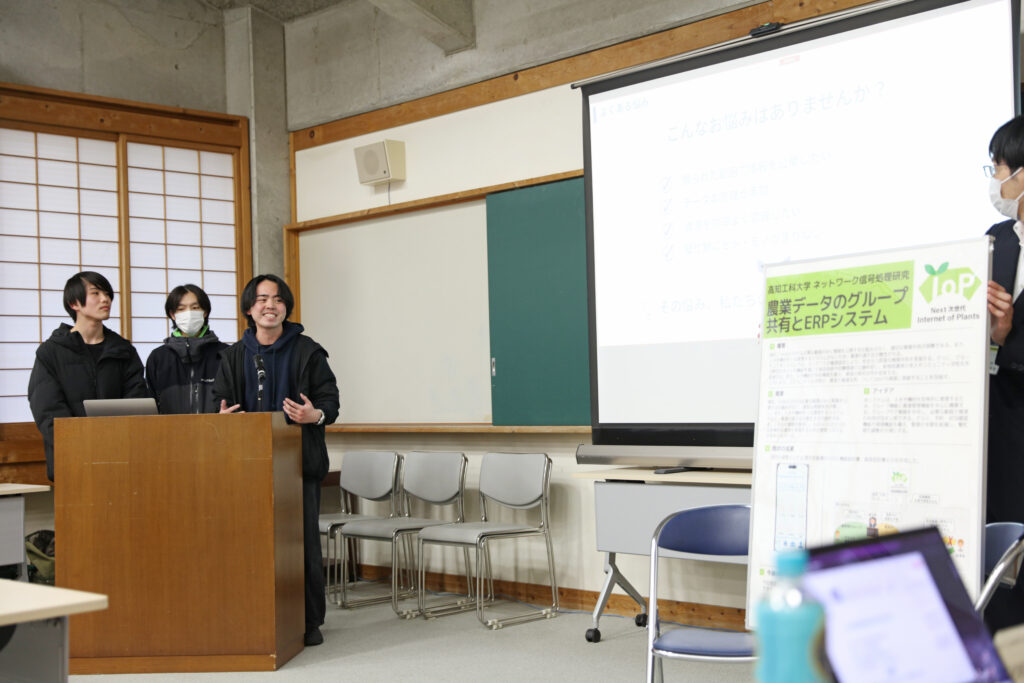

●データ連携基盤活用実証事業報告 (ネポン株式会社)
ネポン株式会社より「高知県研究技術を利用した病害適期防除」の実証報告が行われました。
実証報告では、ナス、シシトウ、ピーマンにおける黒枯病の発生予防や生産者の防除負担の軽減をテーマに、SAWACHIデータベースの温湿度センサーを黒枯病防除アプリと連携させて「黒枯病リスクの見える化」を実施した内容が報告されました。
●ディスカッション「研究技術と既存商流における、新しいビジネス展開」
「研究技術と既存商流における新たなビジネス展開」をテーマに、アイデアソンを行った8チームによるディスカッションが実施されました。ディスカッションでは、農業業界の現状におけるビジネス領域の検討や、AI技術の活用方法、さらには高知県におけるデータ駆動型農業の未来についてなど、多岐にわたる議題が取り上げられ、意見交換の中で新たなビジネスや展開を期待させるアイデアも多数提案されました。
●講評と閉会
本年度の発表会の締め括りとして、今回のコミュニティ成果発表会についてアソシエイト、フェローの方々から講評をいただきました。
・福本昌弘氏(高知工科大学) 写真左
本年度のコミュニティ発表会には、実施事業に地域の学生が参加するといった新たな展開もあり、学生の方々はもちろん、私たち関係者にとっても非常に刺激のある内容になったと思う。
・岩尾忠重氏(高知大学 IoP共創センター)写真中
一次産業に投資を呼び込むことは今後ますます重要になる。今回の報告でも多かったAIを活用した次世代的な取組などには、ぜひその効果を期待したい。
・市川仁平氏(高知県産業振興センター)写真右
技術面のことはもちろん、ビジネス展開の仕方などもとても参考になった。コミュニティも3年目を迎え、これまで築いてきたものが芽吹いてきたように感じる。



